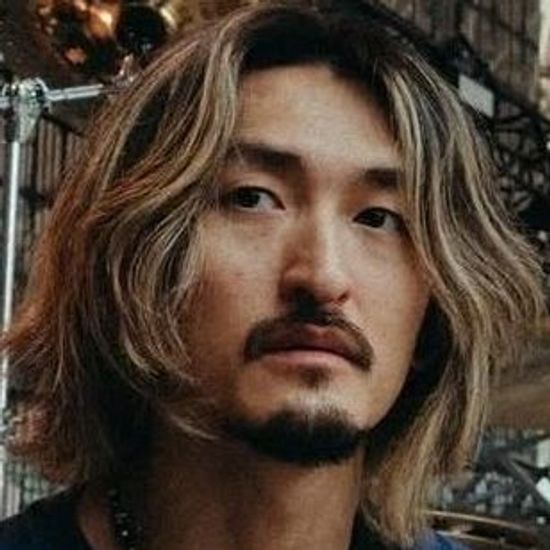引用元のJ-cast様はこちらから
俳優・松下洸平さん主演のドラマ「放課後カルテ」の第8話が、場面緘黙という特定の状況で話せない症状を持つ小学1年生の女の子を描き、話題を呼びました。話題となった場面緘黙は、家庭では話せるのに学校などでは困難な症状で、接し方として無理に話させないことが推奨されています。臨床心理士の角田圭子さんによると、場面緘黙の子どもには質問せず普通に話しかけることが望ましいとされています。このドラマを通じて、場面緘黙への理解が広がることが期待されています。
ドラマ「放課後カルテ」で注目集まる「場面緘黙」とは?
俳優・松下洸平主演の話題作
2024年12月6日に放送された日本テレビ系の土曜ドラマ「放課後カルテ」の第8話が、SNSのXで話題になりました。この回では、「場面緘黙(ばめんかんもく)」の少女が主役として描かれ、視聴者の関心を集めました。家庭では普通に話せるのに、学校など特定の場面では声が出せないというこの症状が大きく取り上げられたのです。
ドラマの内容
このドラマは、小児科医の牧野峻(まきのたかし)が小学校の保健室で子どもたちの「言葉にできないSOS」を読み解き、支援していくストーリーです。原作コミックも人気を博し、ファンを魅了してきました。第8話では、小学1年生の真愛(まな、子役の英茉さん)が家では元気に話せる一方、学校では無口になってしまう様子が描かれました。
真愛ちゃんと場面緘黙
劇中で描かれた真愛ちゃんは、家では元気に話せますが、学校では話せないという「場面緘黙」に悩んでいます。これは、家などでは会話ができるが、特定の状況では困難になるという症状です。身体の緊張が強く自由に動けないといった特徴があり、学校での真愛ちゃんは無表情で、担任の先生やクラスメートに話しかけられても、応答が難しい状態でした。
適切なサポートとは
ドラマ内での学校医の牧野は、真愛ちゃんへの接し方として「無理に話させようとしないこと」や「過剰に褒めることは緊張を招く」といったアドバイスをしていました。また、音楽会では声を出さなくても参加できるような振り付けを取り入れるなど、真愛ちゃんの緊張を和らげる工夫が行われました。
理解と支援の重要性
一方で、クラスメートの一部が「なんで喋らないの?」と問いかける場面もありました。正しい理解がないと、このような無意識のプレッシャーをかけてしまうかもしれません。実際に、場面緘黙の子どもが身近にいる場合、どのように接するのが望ましいのでしょうか。「かんもくネット」の代表で臨床心理士の角田圭子さんは、質問を控え、普通に話しかけることが大切だと述べています。
見えてきた課題と希望
「場面緘黙」というテーマを通して、ドラマは多くの人に子どもたちの見えない悩みやサポートの重要性を伝えることに成功しました。今後、場面緘黙に対する理解が広まり、より多くの子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、社会全体でのサポートが求められます。このドラマをきっかけに、多くの人がこの問題について考えるきっかけとなれば幸いです。